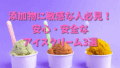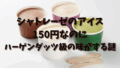私たちの身の回りの食品には、さまざまな添加物が使われています。
スーパーで買った食品の原材料表示を見ると、聞き慣れない名前や数字の羅列を目にすることも。
「添加物」というと何となく不安に感じる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、食品添加物とは何か、安全性はどうなのか、表示の見方などについて、専門知識がない方でも理解できるよう、わかりやすく解説します。
食品添加物とは?基本的な役割と種類
食品添加物とは、食品の製造過程や保存の目的で使用される物質のことです。
日本では約1,500種類もの添加物が認可されており、以下のような役割を担っています。
主な添加物の種類と役割
- 保存料:食品の腐敗や変質を防ぎ、保存期間を延ばす
- 代表例:ソルビン酸、安息香酸Na、プロピオン酸
- 甘味料:砂糖の代わりに甘みを付ける
- 代表例:アスパルテーム、ステビア、キシリトール
- 着色料:食品に色をつける
- 代表例:赤色2号、ベニコウジ、カラメル
- 香料:香りや風味をつける
- 代表例:バニリン、エチルバニリン
- 乳化剤:水と油を混ぜ合わせる
- 代表例:レシチン、モノグリセリド(471)
- 安定剤:食感を良くしたり、分離を防いだりする
- 代表例:グァーガム(412)、カラギーナン(407)
- 酸化防止剤:酸化による変色や風味の劣化を防ぐ
- 代表例:ビタミンC(アスコルビン酸)、ビタミンE
- 漂白剤:食品の色を抜いたり、明るくしたりする
- 代表例:次亜塩素酸Na、二酸化硫黄
天然添加物と合成添加物の違い
添加物は大きく天然添加物と合成添加物に分けられます。
- 天然添加物:自然界に存在する物質から抽出されたもの
- 例:クチナシ色素、ベニバナ色素、ペクチンなど
- 合成添加物:化学的に合成されたもの
- 例:ソルビン酸K、安息香酸Na、タルトラジンなど
ただし、天然だから必ず安全、合成だから危険というわけではない点には注意が必要です。
添加物の安全性:許可制度と基準値
日本の添加物許可制度
日本では、食品添加物は食品衛生法に基づく「指定添加物」制度のもとで管理されています。
添加物として使用するには、厚生労働省による安全性評価を経て、使用が認められる必要があります。
安全性評価の仕組み
添加物の安全性評価は、以下のような厳格なプロセスで行われます。
- 動物実験による毒性評価
- ADI(一日摂取許容量)の設定
- 使用基準(使用できる食品や使用量の上限)の設定
例えば、保存料として使われるソルビン酸のADIは体重1kgあたり25mgとされています。
60kgの人なら1日に1,500mgまでなら安全とされる計算です。
海外との違い
国によって認可されている添加物や基準値は異なります。
例えば、EUでは認可されていない着色料が日本では使われているケースもあれば、逆に日本では禁止されているけれど海外では使用されている添加物もあります。
海外製品を購入する際には、この違いに注意が必要です。
表示の見方と見落としがちなポイント
食品表示法での添加物表示ルール
日本では、食品表示法により、使用した添加物を原材料表示欄に記載することが義務付けられています。
ただし、表示方法には以下のようなルールがあります。
- 物質名表示:「ソルビン酸K」「アスパルテーム」など物質名で表示
- 用途名併記:「保存料(ソルビン酸K)」「甘味料(アスパルテーム)」など
- 一括名表示:「香料」「着色料」など、特定のカテゴリーのみ一括表示が許可されている
数字表記の意味
原材料表示で見かける3桁の数字は、国際的な食品添加物の識別番号「INS番号」です。
例えば「乳化剤(471)」は「乳化剤(モノグリセリド)」を意味します。
表示免除の添加物
以下のような場合、添加物表示が免除されることがあります。
- 加工助剤:製造過程で使用されるが、最終製品にはほとんど残らないもの
- キャリーオーバー:原材料に含まれていた添加物が、最終製品に微量に移行するケース
例えば、加工食品に使われる小麦粉の製造時に使われた添加物などは表示されない場合があります。
より詳しい添加物の見分け方については、食品添加物ハンドブック 最新版で解説されています。
添加物が多く含まれやすい食品とは
以下のような食品は、一般的に添加物の使用が多い傾向があります。
- 加工度の高い食品
- インスタント食品
- レトルト食品
- 冷凍食品(特に調理済みのもの)
- 長期保存を目的とした食品
- 菓子類(特に色鮮やかなもの)
- ハム・ソーセージなどの加工肉
- 缶詰・瓶詰食品
- 見た目や食感を重視した食品
- 市販のケーキやデコレーション菓子
- アイスクリーム(特に色や食感にこだわったもの)
- 練り製品(かまぼこ、ちくわなど)
これらの食品を避ける必要はありませんが、摂取頻度や量に気をつけるといいでしょう。
特に避けたい添加物については、ワースト添加物に詳しくまとめられています。
添加物との上手な付き合い方
自分に合った選び方
添加物との付き合い方に「正解」はありません。
自分の価値観や体質に合わせて選ぶことが大切です。
- 体質的に気になる方
- 特定の添加物で体調不良を感じる場合は、その成分を避ける
- オーガニック食品や無添加食品を選ぶ
- 生鮮食品中心の食生活を心がける
- バランス重視の方
- 加工食品も適度に利用しつつ、全体のバランスを取る
- 特に気になる添加物(着色料など)だけ注意する
- 手作り料理も取り入れる
家庭でできる対策
- 原材料表示を確認する習慣をつける
- 同じ種類の食品でも、添加物の少ないものを選ぶ
- 野菜や果物はよく洗う(残留農薬対策)
- 時間に余裕があるときは手作りを楽しむ
日常生活ではなかなか難しいこともありますが、できることから少しずつ取り組むのがおすすめです。
最後に:バランスの取れた視点を持つために
添加物に対しては、過度に恐れすぎず、かといって無関心にもならない姿勢が大切です。
添加物のメリットも理解する
- 食品の安全性確保(腐敗防止)
- 食生活の多様化や利便性向上
- 食品ロス削減への貢献
これらは現代の食生活を支える重要な役割でもあります。
情報源を選ぶ
添加物に関する情報は玉石混交です。
情報源としては以下を参考にするとよいでしょう。
- 厚生労働省や消費者庁などの公的機関
- 日本食品添加物協会などの専門団体
- 科学的根拠に基づいた書籍や記事
SNSやネット上の情報は、ソースを確認し、複数の情報源で確認することをお勧めします。
最終的な判断は自分で
添加物に対する考え方は人それぞれです。
過度な不安や思い込みではなく、正しい知識をベースに、自分に合った食品選びをすることが大切です。
さらに詳しく知りたい方におすすめの書籍
添加物について更に詳しく知りたい方は、以下の書籍がおすすめです。
それぞれ異なる視点から食品添加物について解説しています。
選び方を知りたい方に

食品添加物ハンドブック 最新版 どれを選べばいいの?/渡辺雄二
日常的な買い物で役立つ、食品添加物の選び方をわかりやすく解説した実用書です。
添加物の基礎知識から具体的な商品選びのコツまで幅広く学べます。
添加物の懸念点を知りたい方に

一般的に使われている添加物の影響について詳しく解説した本です。
日常的に口にしている食品に含まれる添加物について知識を深めたい方におすすめ。
具体的な避け方を知りたい方に

ワースト添加物 これだけは避けたい人気食品の見分け方/中戸川貢
特に気をつけたい添加物とその見分け方について詳しく解説されています。
添加物に敏感な方や、体質的に気になる方におすすめの一冊です。
※これらの書籍は様々な視点から書かれています。バランスよく情報を取り入れることをおすすめします。
関連記事